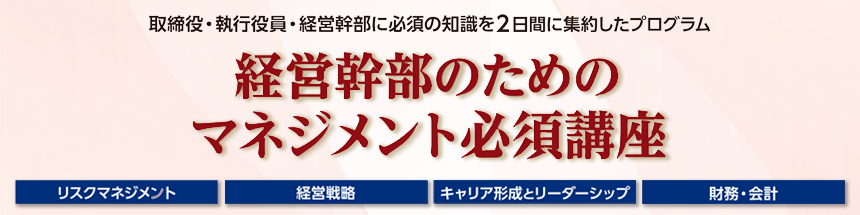経営幹部のためのマネジメント必須講座
| 会期 |
1会期2日間/年2回開催
2025年9月17日(水)〜9月18日(木)の2日間
2025年11月5日(水)〜11月6日(木)の2日間 |
| 会場 |
クロス・ウェーブ梅田(大阪市北区) |
| 参加対象 |
- 新任の取締役や執行役員の方
- 役員候補の方
- 事業部長などの経営幹部の方
- 経営者として必要な基礎知識を改めて学びたい方
|
開催のねらい
日本能率協会ではトップマネジメント(取締役・執行役員・経営幹部)の経営力向上が、企業活力や競争力向上のための最重要課題であるとの認識に立ち、トップマネジメント対象研修を40年以上にわたって実施してまいりました。これまで、10,000名を超える役員・経営幹部の方々が学ばれています。
加速度的に変化する経営環境において迅速な経営判断が求められる一方、企業活動に対する社会の眼は日に日に厳しくなっており、トップマネジメントには、より一層高い使命感・倫理観が求められています。また、グローバル化や社員の価値観・就業形態の多様化が進む中、明確なビジョンを組織に浸透させ実現する高いコミュニケーション能力や、組織・人材に対する深い洞察が必要です。
そのため、経営幹部としての考え方や役割についての認識を新たにするとともに、これからのマネジメントに必要な知識とスキルを、今改めてしっかりと身につけておく事が重要です。
本講座は、取締役・執行役員・経営幹部に必須の知識である、「リスクマネジメント」「キャリア形成とリーダーシップ」「経営戦略」「財務・会計」のエッセンスを2日間で集中して学んでいただくプログラムです。ゲスト講演では経営者の方から「リーダーシップ」「キャリア」についてをお話いただき、対話を重ねることで、役員・経営者として何をなすべきかの解像度をより高めていただけます。
プログラム
1日目[10:00~17:30] 懇親会[17:45~19:30]
※プログラム内容、講義順番は都合により変更となる場合がございますのであらかじめご了承願います。
講義(0)オリエンテーション(経営幹部に求められる基本姿勢と役割責任)
|
講義(1)内部統制と全社的リスクマネジメント(ERM)
上場、非上場を問わず企業を取り巻く環境は複雑になり、企業は様々なリスクを抱えています。現場のマネジャーとは異なり、経営幹部には企業全体を俯瞰的に観て適切な意思決定とモニタリングが求められます。そのためには内部統制と全社的リスクマネジメントの理解と実践が不可欠です。安全管理やBCP等との違い、リスクの分類(事業機会、事業活動、上場等)とマネジメントをケーススタディ方式で学習します。さらには最近の企業不祥事の深層原因を考察します。参加者同士の討議も行い、自社の経営会議の運営にも反映できます。
-
内部統制の基本
- 内部統制の沿革、目的、基本要素、体制(スリーライン)
- 子会社等に役員として出向した際の内部統制の活用[グループ討議]
-
最近の企業不祥事の事例から何を学ぶか
- 企業不祥事の分類(過失と不正、自己利益か組織保身か等)
- 組織的不正(製造業、流通業等)の深層原因の考察[グループ討議]
- 企業不祥事の根底にある組織的認知バイアス、日本語文化の弱み
- 従業員をどう動機付け、再生と信頼回復を図るか[グループ討議]
-
全社的リスクマネジメント(ERM)
- 企業成長ステージに応じたリスクの体系(事業機会、事業活動、上場)
- ハザード、インシデント、BCP、クライシスマネジメントとの関連
- サスティナビリティ、TCFDリスク、グローバルリスク
- 全社的リスクマネジメントのプロセス、取締役会等の役割等[グループ討議]
-
経営会議の運営改革
- 部門長ではなく経営幹部としてどう経営会議に臨むか、運営を改革するか
- 歴史から学ぶ、株主等ステークホルダーのグローバル化への対応等
「部門の長」から「企業全体を俯瞰出来る経営幹部」へと導きます
【講義(1)担当】星野 芳昭 氏
株式会社スター・ガバナンス
代表取締役、ガバナンスコーチ
慶應義塾大学商学部卒業後、JMAでの実務経験を経て1985年よりコンサルティング会社にて上場企業等の組織改革、業務改革、業績評価制度、マネジメントサイクル定着化等に取り組む。1995年より内部統制とリスクマネジメント、2005年よりサスティナビリティ(ESG)経営に取り組む。2013年に独立し、取締役会の実効性評価、取締役・執行役員・選抜執行役員候補者等のトレーニングとコーチング等に取り組む。行動変容と業績への反映など定量的なアプローチが特徴。
|
講義(2)経営幹部としてのキャリア形成とリーダーシップ
本セッションは、実際に上場企業の代表取締役社長のご経験を持つ方をお招きして、自身のこれまでのキャリアやご苦労されたことなどをお聴きします。
さらに「トップとしてのリーダーシップ」や「役員としてのキャリア形成」などをグループ討議していきます。
討議結果はゲスト講師とファシリテーターが講評し、今後のキャリア形成やスキルの向上に活かしていただきます。
- 経営者講演
- 質疑応答
- グループ討議
- 講評(経営者講師とファシリテータ2名による)
【2025年 ゲスト講演】國井 総一郎 氏
株式会社ノーリツ 相談役
兵庫県公立大学法人 理事長
|
講義(3)参加者交流・懇親会
|
2日目[9:30〜17:00]
講義(4)競争優位の経営戦略と事業創造
全体最適・将来最適を見据えながら、成長分野への投資など新たな打ち手とともに、構造も的確に変革していかなければなりません。限られた経営資源の配分と有効活用を考え、優先順位を決断する。
本セッションでは、事業と経営戦略で役員に求められる視点を学びます。
-
経営戦略とリンクした事業創造
- 価値観とステークホルダー戦略:経営戦略の前提
- ビジョンと経営戦略:戦略的視点の重要性
- ドメインの定義
- 経営戦略と資源
- 競争優位の戦略
- 戦略策定のプロセス
- 事業創造の戦略
-
ビジネスモデルの考え方
- ビジネスモデルの意義
- ビジネスモデルの構造
- ビジネスモデルの編成原理
不透明な時代を生きぬくための経営戦略について考えましょう
【講義(4)担当】金井 一賴 氏
大阪大学名誉教授
大阪公立大学大学院 都市経営研究科 教授
神戸大学大学院 経営学科研究科 博士課程修了、弘前大学 人文学部、滋賀大学 経済学部、北海道大学経営学部、同大学大学院 経済学研究科、大阪大学大学院 経済学研究科 教授、大阪商業大学 総合経営学部 教授を経て2018年より青森大学学長(2023年3月退官)。
日本ベンチャー学会会長、組織学会評議員、企業家研究フォーラム理事他多数の要職にある。
<研究分野>経営組織、経営戦略、企業家活動、ベンチャー創造とクラスター 等
<主要著書>『ベンチャー企業経営論』『大学発ベンチャー:新事業創出と発展のプロセス』『経営戦略一理論性・創造性と社会性の追及』 他
|
講義(5)財務・会計の重要ポイント
企業の持続的成長と企業価値向上のために「コーポレートガバナンス・コード」では、自社の資本コストと KPI(重要業績評価指標)の開示が求められています。KPIと資本コストは、経営幹部として適正な経営 判断や意思決定を行う上でも重要であり、その正しい知識と実践に向けて分かりやすく解説します。
-
利益測定の誕生から現在の財務報告制度まで
- 利益測定の重要性
- 企業会計をめぐる3つの法律
- 会計の政治化・国際化・電子化
-
KPIと資本コストのイントロダクション
- 資本コストの把握とKPIの開示要求
- 積極的な開示例
- 日本企業と投資家の認識ギャップ
-
KPIと資本コストの考え方と実践
- KPIと資本コストはなぜ重要か?
- 代表的な収益性尺度:ROEとROA
- 近年注目されているROICとは?
- 資本コストの理論と実践
-
企業価値評価の実践
- 各種企業価値評価モデル
- 割引キャッシュフロー法 (Discounted Cash Flow Model)
- 配当割引モデル (Discounted Dividend Model)
- 残余利益モデル (Residual Income Model)
- 残余利益モデルの実践
経営者に必須な数字を分かりやすく説明します
【講義(5)担当】石川 博行 氏
大阪公立大学大学院
経営学研究科 教授
神戸大学経営学部卒業、神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程修了、博士(経営学)、大阪市立大学商学部専任講師、大阪市立大学大学院経営学研究科准教授を経て、2009年より現職。
<研究テーマ>会計情報を用いた企業分析と企業評価。企業活動が会計報告書にとりまとめられるプロセスと、それが株式市場に伝達されたときの経済的効果に関する理論的・実証的研究。
配当や自社株買いといった株主還元の意思決定と、それらのペイアウトが株式市場にどのような影響を与えているのかについての理論的・実証的研究。
<主要著書>『配当政策の実証分析』、『株価を動かす配当政策 コロボレーション効果の実証分析』、『会社を伸ばす株主還元』等
|
参加者の声
- 最新事例に更新のうえ解説いただき、自身のなすべきことの解像度が高まり、見識を深めることができた。
- ディスカッションでは直面している課題を他業種の方と対話でき有意義であった。
- 説明もわかりやすく2日間中身の濃い講座だった。経験からなんとなく感じていたことを体系的、論理的に学ぶことができた。
- 実務経験で得た知識を改めて講義として学び直したことで、過去の行動を振り返り確信を持てるもの、改めるべきものがよくわかった。
- 今の意識がどれだけ足りてないかを感じ、今後の課題が見つけることができた。
- 役員になって意識改革が必要だと感じていた中、基本部分と要点が2日間でカバーできており実例による説明が非常に役に立った。